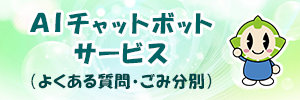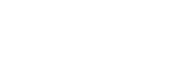ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
議会用語一覧
香芝市議会は、市民にわかりやすい議会運営を目指しています。本会議でよく使われる議会用語をまとめましたので、本会議の傍聴や会議録閲覧の参考にしてください。
あ行
| 委員会 | 本会議で付託された議案や意見書、請願書等について、専門的に審査をするための機関です。香芝市議会では、各常任委員会(総務建設・福祉教育)および議会運営委員会が設置されています。委員の任期は1年です。 |
|---|---|
| 委員会付託 | 議案の審査を詳細かつ効率的に行うため、各常任委員会に議案や請願の審査を任せることです。付託された事件は、委員会での審査または調査が終わるとその審査結果について委員長から議長に対し委員長報告書を提出される。この報告書の提出によって委員会に付託された事件が議会に返付され、これをまって議会の会議の議題とすることとしていると解しています。 |
| 委員長報告 | 委員会は付託議案の審査を終了したときは、議案等の審査概要と結果について経過報告を文書で議長に提出するとともに本会議場で委員長報告を口頭で行います。その後、委員長報告に対する質疑、討論、採決と進みます。 |
| 意見書 | 市政を進めていくうえで、市単独では解決が難しい問題があります。このようなときに、市議会から意見書を国会や関係行政庁へ提出し問題の解決を働きかけます。 |
| 一部事務組合議会の議員 | 行政の効率化を図るため、消防、水道事業、ごみ処理事業など特定の事務を関係する市町村で共同処理しています。一部事務組合は特別地方公共団体として議会が置かれ、香芝市議会から議員を選挙しています。一部事務組合には、奈良県葛城地区清掃事務組合、香芝・王寺環境施設組合、奈良県広域消防組合があります。 |
| 一問一答方式 (いちもんいっとうほうしき) |
香芝市では、質問を行いこれに対する答弁を行い、第2問、第3問と順次同じように質問と答弁を繰り返す方法です。これまでの一括質問、一括答弁に比べてわかりやすい議会運営となりました。 |
| 一事不再議 (いちじふさいぎ) |
本会議で一度議決された議案は、同一会期中は再び議案とすることはできないという原則です。 ただし、次の議会で再提出することは可能です。 |
| 一般質問 | 議員が市政一般について質問することです。 香芝市議会では、一般質問の発言時間は40分(答弁除く)の発言時間の制限を設けています。 |
| 延会 | 議事日程に記載した事件が終了せず、他の日に伸ばしてその日の会議を閉じることです。 |
| 演壇 | 議員および執行部が提案理由の説明や答弁を行う場所です。 議長席の前に場所を設けています。 |
か行
| 開会 | 議会を開くことです。 本会議初日に議長が宣言し、議会が始まります。 |
|---|---|
| 会期日程 | 議会が活動できる期間(開会から閉会まで)です。本会議初日に会期の決定を行います。会期は本日から○月○日までの○日間という定め方をします。 |
| 開議 | 議長が宣言することで、その日の本会議を開くことです。 |
| 会議時間の延長 | 会議時間は午前9時から午後5時までと会議規則に定められています。午後5時近くになっても審議が終わらない場合、議長が会議時間の延長を宣告します。宣告により、その日の午後12時まで延長できます。 |
| 会議録 | 本会議の記録です。会議録は、図書館、議会ホームページで閲覧することができます。 |
| 会議録署名議員 | 会議録に署名する議員を議長が本会議で指名します。地方自治法で2人以上の議員を指名することになっています。 |
| 会派 | 多数決を原則とする市議会の中において、自らの政策の実現や発言権の確保などのために、同じような考え方をもった議員同士が集まり活動しています。このような議員のグループのことを「会派」と呼んでいます。 |
| 監査委員 | 地方自治体の財政や事業に対して監査を行う機関です。香芝市の監査委員は2名であり、そのうち1名は議員から選出されます。 |
| 可決・否決 | 議案に対して賛成の場合は可決、反対の場合は否決という意味の議決です。 |
| 議案 | 市長や議員が議会に提案する案件で議決の対象となるものです。予算、決算、条例改正、意見書、決議、人事案件などがあります。 |
| 議員提案 | 議案は、通常市長から提案されますが、議員もしくは委員会からも提案することができます。 香芝市議会では、議員提案に必要な提出者は2名以上です。 議員提案では主に意見書、発議、決議、条例案等が提案されます。 |
| 議員派遣 | 調査、研究のため必要があるときは、議会の議決(派遣の目的、派遣先、派遣期間、派遣議員)で議員を派遣しています。 議会の閉会中で議会の議決が得られない場合は、議長が決定し次の議会で報告しています。 |
| 議会運営委員会 | 議長の諮問および議会運営について協議する委員会です。 香芝市議会では、各会派から所属議員数に応じて選出を行い6人で構成しています。 委員会には、議長がオブザーバーとして出席しています。 |
| 議席 | 本会議で議員が着席する場所です。 議席には、1番から16番までの議席番号と氏名票が置かれています。 |
| 議事日程 | 本会議の1日の予定表です。 議事日程に記載する事項は、会議の日時、会議に付する事件およびその順序が記載されます。議員、執行部、傍聴者にもその日の議事日程が配布されます。 |
| 議場 (ぎじょう) |
本会議が開かれる場所です。香芝市議会は5階にあります。議場には傍聴者用の席が用意されていますので、香芝市議会傍聴規則をじゅんしゅしていただければ、どなたでも傍聴できます。 |
| 議長・副議長 | 議会を代表するのが議長です。議長・副議長は議員の中から選挙で選ばれます。 副議長は議長が欠けたとき、不在のときに代わりを務めます。 |
| 休会 | 会期中において議案調査や事務整理のため、議会が開かれないことです。市の休日も休会となります。 |
| 起立採決 (きりつさいけつ) |
議案に対して議員が賛否の意思表示を起立により行う方法です。 |
| 継続審査 (けいぞくしんさ) |
委員会に付託された議案について、定例会中に審査が終了せず、なお引き続き検討が必要な場合に閉会中(議会終了後)に審査を行うことができます。 委員会で事件の継続審査を決定し、本会議での議決を必要とします。 |
さ行
| 採決 | 議長が議員に議案の賛否の意思表示を求めることです。 |
|---|---|
| 採択・不採択 | 委員会に付託された請願(陳情)について、採択の場合は賛成、不採択の場合は反対という意味の議決です。 |
| 散会 | 1日の議事日程に記載した事件が終了し、その日の会議を閉じることです。 |
| 質疑 | 市長や議員から提案された議案に対して、疑問点を提出者に問い質すことです。質疑は、会議規則で自己の意見を述べることはできないとされています。 |
| 質問席 | 一問一答方式の採用により、代表質問・一般質問の第2問以降の質問は質問席から行います。 |
| 指名推薦 | 議会における選挙は、通常投票により行われますが、議員の中に異議がなければ指名された人を当選人とする方法です。 |
| 趣旨採択 (しゅしさいたく) |
請願について、その内容は妥当であるが、市の事務事業の内容や、財政事情等から願意を実現することが困難な場合などに、採択には至らないものの「趣旨には賛成である」という意味で採られる意思決定の方法です。 |
| 紹介議員 | 請願を議会に提出するために必要な1人以上の議員です。 紹介議員は請願の内容に賛同する者で、香芝市議会では委員会付託後、委員会で説明を求められます。 |
| 招集 (しょうしゅう) |
議会を開くために議員に日時、場所を指定して集合することを求めることです。本会議は市長が招集しますが、委員会は委員長が招集します。 |
| 承認・不承認 | 専決処分など市長の権限で決定された事項に対し、承認の場合は賛成、不承認の場合は反対とする意味の議決です。 |
| 上程 (じょうてい) |
事件を議事日程の中に組み入れて議題とすることです。 |
| 常任委員会 | 本会議で付託された議案について詳細に審査を行うのが委員会です。所管ごとに担当する委員会が定められ、香芝市議会には2つの委員会(総務建設委員会・福祉教育委員会)があります。 |
| 所管事務調査 (しょかんじむちょうさ) |
付託を受けた議案などの審査以外に、所管する事務に関して行う調査のことです。 |
| 除斥 (じょせき) |
議案審議を行う時、議案の内容と利害関係のある議員があるときは、公平を保つため該当する議員を審議が終了するまで、議場から退席させることです。 |
| 審議未了 (しんぎみりょう) |
議案について結論(可決・否決等)が出ないまま定例会が終了することで、提案された議案が消滅することです。 |
| 請願 (せいがん) |
意見や要望を行政に反映させるため、その内容を議会に対して文書で提出することです。請願には1人以上の紹介議員が必要です。請願は所管する委員会で審査を行い、本会議で採決されます。 |
| 政務活動費 |
地方自治法第100条第14項、第15項および香芝市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、香芝市議会議員に一人当たり4万5千円/月を交付しています。政務活動費で議員の調査活動を行った場合、年度終了後、収支報告に領収書等を添付し使途を明らかにしています。 |
| 専決処分 (せんけつしょぶん) |
議会を招集する時間的余裕がないとき、市長が議会に代わって議案を決定することです。専決された議案は次の議会に上程され承認するかどうか審議を行います。 |
た行
| 代表質問 | 市長施政方針等に対して会派を代表して質問することです。 香芝市議会では、代表質問の発言時間は40分(答弁除く)の発言時間の制限を設けています。 |
|---|---|
| 陳情 (ちんじょう) |
請願と同様の文書ですが、紹介議員の必要がありません。 |
| 通告 | 議員が代表質問・一般質問をする際に、事前に議長に発言内容を伝えることです。通告は文書で行われ能率的な議会運営に役立っています。 |
| 定足数 (ていそくすう) |
会議を開く時に最低限必要な人数のことです。 |
| 定例会 | 定期的に開催される議会で年4回開くことが条例で定められています。 香芝市議会では3月、6月、9月、12月に招集されます。 |
| 同意・不同意 | 人事案件の議案に対して同意の場合は賛成、不同意の場合は反対するという意味の議決です。 |
| 討論 | 議案に対して賛成または反対の意見を表明し、議員を自分の意見に同調させることです。 討論を行う場合、討論交互の原則により議長は、反対者、賛成者を交互に発言させます。 |
| 特別委員会 | 議会の議決により特別に設置される委員会です。委員会設置の目的が完了したときは消滅します。 香芝市議会では3月定例会で設置される予算特別委員会、9月定例会で設置される決算特別委員会などがあります。 |
な行
| 認定・不認定 | 決算特別委員会に付託された議案に対して認定の場合は賛成、不認定の場合は反対という意味の議決です。 |
|---|
は行
| 発言の取り消し・訂正 | 取り消しとは、不適当な発言を議事録から削除することで、訂正とは、単純な間違い発言を変更することです。 取り消しは、議会の許可を要しますが、訂正は議長の許可となります。 |
|---|---|
| 反問権 (はんもんけん) |
議員の質問に対し、論点・争点を明確にするため、理事者が、議員に反問することができるものです。反問権は、質問と答弁が準備された「なれ合い的な方式」からの脱却や、議会機能の強化並びに議員の資質の向上を図ることを目的としています。 |
| 閉会 | 議会を終了することです。 |
| 報告 | 専決処分、繰越明許費、決算報告などの案件をいいます。 専決処分は承認の手続きが必要となりますが、それ以外は受理という扱いになります。 |
| 報酬 (ほうしゅう) |
非常勤特別職である議員に対して、その職務の対価として一定の金額が支払われます。香芝市議会では、議長63万円,副議長53万円、議員50万円が月額で支払われています。 |
| 傍聴 (ぼうちょう) |
市議会の会議状況について、本会議、常任委員員会、議会運営委員会、特別委員会を傍聴することができます。傍聴を希望される方は、市役所5階議会事務局で、傍聴人受付簿に住所および氏名を記入していただくだけで傍聴することができます。 |
ら行
| 臨時会 | 年4回の定例会以外に臨時的に議会を開く必要がある場合に招集されます。 |
|---|