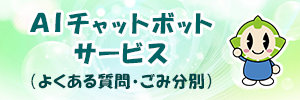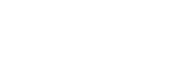本文
出産したとき(出産育児一時金)
被保険者が出産したときに支給されます。
妊娠12週(85日)以上であれば、死産、流産でも支給されます。
出産育児一時金の支給額
-
産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に出産した場合50万円(令和5年3月31日までの出産は42万円) (詳しくは「産科医療補償制度とは」をご覧ください。)
- 同制度に加入している医療機関で在胎週数22週未満の出産(死産・流産含む)の場合や、同制度に未加入の医療機関(海外出産含む)で出産した場合48万8千円 (令和4年1月1日~令和5年3月31日までの出産は40万8千円)
支給の方法
支給の方法は「本人に支給する方法」と「国保が医療機関等に直接支給する方法(直接支払制度)」があります。どちらを選ぶかは分娩される医療機関等で、ご確認ください。
※一部の医療機関等で、直接支払制度を導入していない場合がありますのでご注意ください。
「本人に支給する方法」を選んだ時
- 出産後、費用を医療機関に支払う。
- 出産育児一時金の支払請求
申請に必要な物
- 出産費用の内訳を記した明細書および領収書
- 医療機関等が交付した直接支払制度の利用に関する合意文書
- 世帯主の振込口座がわかるもの
- 申請に来るかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 違う世帯のかたが申請に来る場合、委任状
申請の手順
- 香芝市役所の国保医療課に出産育児一時金の支給申請をする。
- 指定口座に振り込まれる。
「直接支払制度」を選んだ場合
- 医療機関の請求金額が出産育児一時金より多いときは、出産育児一時金の額が香芝市から直接医療機関に支払われるので、請求金額と出産育児一時金の差額を医療機関にお支払いください。
※医療機関に支払う金額=請求金額-出産育児一時金 - 医療機関の請求金額が出産育児一時金より少ないときは、医療機関の請求金額が国保から直接医療機関に支払われるので、残りの金額を国保医療課に請求ください。
※国保医療課に請求する金額=出産育児一時金-医療機関の請求金額
申請に必要な物
- 出産費用の内訳を記した明細書
- 医療機関等が交付した直接支払制度の利用に関する合意文書
- 世帯主の振込口座がわかるもの
- 申請に来るかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 違う世帯のかたが申請に来る場合、委任状
申請の手順
- 香芝市役所の国保医療課に支給申請をする。
- 指定口座に振り込まれる。
産科医療補償制度とは
産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性まひとなったお子様とご家族の経済的負担を補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、再発防止に役立つ情報を提供する制度です。
この制度は2009年に創設され、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営されています。
補償金
補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。
補償の対象(2022年1月1日以降に出生のお子様より補償対象の基準が変わります。)
次の1から3の基準をすべて満たす場合、補償対象となります。なお、お子様の出生年によって基準が一部異なります。
1.<2015年から2021年12月31日までに出生のお子様の場合>
在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
<2022年1月1日以降に出生のお子様の場合>
在胎週数28週以上
2.身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ
3.先天性や新生児期の原因によらない脳性まひ
補償申請できる期間
補償申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。(ただし、極めて重症であって、診断が可能となる場合は、生後6ヶ月から補償申請可能)
詳細につきましては、運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構の産科医療補償ホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>を参照いただくか、分娩機関または下記専用コールセンターに問い合わせてください。
産科医療補償制度専用コールセンター
0120-330-637 受付時間:午前9時から午後5時(土日祝日・年末年始除く)
ホームページ:http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/<外部リンク>