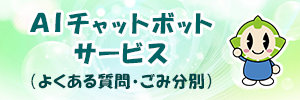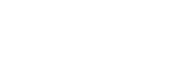本文
保険料の軽減
前年の所得が一定額以下のかたに対する軽減措置(法定軽減)
世帯の前年中の合計所得が法令で定められた下表の基準を下回っている場合は、保険料のうち、均等割額と平等割額が所得に応じて軽減されます。軽減に該当しているかたは、あらかじめ軽減後の金額で納付通知書を送付しますので、申請は不要です。
令和7年度軽減基準
| 軽減割合 |
軽減判定所得の基準(令和6年中の所得) |
|---|---|
| 7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+(30万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 2割軽減 |
基礎控除額(43万円)+(56万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 軽減割合 |
軽減判定所得の基準(令和5年中の所得) |
|---|---|
| 7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+(29万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 2割軽減 |
基礎控除額(43万円)+(54万5千円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
(注)
- 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等所得があるかた(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円超または65歳未満で60万円超)のことです。
- 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行となったかたで、引き続き同じ世帯にいるかたのことです。ただし、世帯主変更等があった場合には特定同一世帯所属者ではなくなります。
軽減判定の注意点
- 軽減の判定は4月1日時点で行い、年度途中での被保険者等の増減による再判定は行いません。
- 世帯主および被保険者全員の所得の申告が必要です。所得の申告をしていないかたがいると軽減判定ができず、正確に保険料が決定されませんので、必ず所得の申告をしてください。
- 軽減判定所得は、以下に示すものは保険料の算定とは異なる方法により算出します。
- 前年12月31日において65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額が軽減判定基準額となります。
- 土地や建物等の譲渡所得は、特別控除前の額が軽減判定基準額となります。
- 事業専従者控除があるかたは、控除前の額が軽減判定基準額となります。
- 専従者給与があるかたは、軽減判定基準額には含みません。
未就学児の国民健康保険料均等割額の軽減措置について
子育て世代への経済的負担軽減の観点から、一律に未就学児の均等割額が5割軽減されます。すでに前項の法定軽減を受けている世帯は、法定軽減後の均等割額から5割軽減となります。
なお、軽減措置に係る申請は不要ですが、所得未申告世帯については軽減適用されない場合がありますので、所得の申告をお願いします。
後期高齢者医療制度の創設にともなう軽減
国保被保険者が一人の世帯になったとき
後期高齢者医療制度に移行するかたがいることにより、国保被保険者が一人の世帯(特定世帯※)となるかたは、対象となってから5年間は医療分・後期高齢者支援分の平等割(世帯割)が2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減されます。軽減に該当しているかたは、あらかじめ軽減後の金額で納付通知書を送付しますので、申請は不要です。
なお、世帯主が変更となったときは適用対象外となります。
他の健康保険の被扶養者から国保に加入したとき
被用者保険(社会保険など)の加入者が後期高齢者医療制度に加入するために、これまでそのかたの被扶養者であった65歳以上のかた(旧被扶養者といいます。)が国保に加入する場合、所得割は免除、均等割は資格取得の日から2年間に限り半額になります。また、旧被扶養者のみの世帯であれば平等割も資格取得の日から2年間に限り半額になります。ただし、均等割額・平等割額の半額については、7割軽減・5割軽減に該当する世帯は除きます。
申請が必要となりますので、下記の物を持って、国保医療課で申請してください。
申請に必要な物
- 社会保険等の保険者が発行する資格喪失証明書等(旧被扶養者となったことを確認できる書類)
- 窓口にお越しいただくかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 別世帯のかたが届出される場合、委任状
非自発的失業者の軽減
会社の倒産・解雇、雇い止めなどにより自己都合によらない非自発的失業者となったかたの保険料について、失業から一定期間、保険料を軽減します。
非自発的失業者の保険料の軽減
対象者
離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が11,12,21,22,31,32,23,33,34に該当するかた
※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。
軽減内容
所得割について、前年の給与所得をその100分の30とみなして計算します。
(給与所得以外の所得や、対象となる方以外の所得は軽減対象ではありません。)
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの保険料が、軽減の対象となります。
申請に必要な物
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 世帯主と対象となる方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
出産被保険者の軽減
出産被保険者がいる世帯について、産前産後期間相当分の保険料が軽減されます。
出産被保険者の保険料の軽減
対象者
国民健康保険の加入者で、出産予定または出産した方
※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産、人工妊娠中絶、早産も含みます。
対象期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
※ただし、令和6年1月以降、該当する月に限ります。
軽減額
令和6年1月以降、対象となる期間の所得割額と均等割額の全額
届出に必要なもの
- 出産予定日(出産日)と単胎妊娠・多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳の写し等)
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 世帯主と対象者の方のマイナンバーを確認することができる書類
- 別世帯の方が届出される場合、委任状
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
※出産予定日の6か月前から届出することができます。