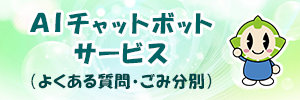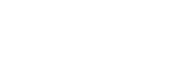本文
(1)農産物の変遷と農家の経済
近代産業の発展と人びとのくらし
(1)農産物の変遷と農家の経済
大和の国中では、年貢の銀納が認められるようになった江戸時代の中期ごろから、綿花や菜種などの商品作物の栽培が盛んであった。
それは、現金収入の多い換金作物であるという理由だけでなく、降雨量の少ない自然条件下で、奈良盆地の水不足を軽減し、水田の用水を確保するためにも必要であった。
このことでもわかるように、奈良盆地における中心的な農産物は米穀であり、水稲栽培を軸にした作付け計画が主流になっていた。
したがって、農家の現金収入源としての綿花や菜種の栽培は、家計の余裕を生みだすための副次的な作物として、江戸時代以来の長い伝統があった。
明治十年代のなかばには、関屋村で五戸、磯壁村で三十余戸の農家が綿花を栽培していたし、各村々の産物として綿実があがっている。
そのうえ婦女子の副業的な仕事として紡績機織が盛んで、多くの農家は菜種や綿花の栽培と加工に関係した仕事で相当の収入をあげていたようである。
ところが、明治二十年代を境にして、この二つの作物の栽培が急速に減少していく。
綿花は良質の外国産綿花の輸入に圧迫されたためであり、菜種は石油ランプの普及による燈油の需要減少がその原因であった。
この大打撃をうけた村々に新しく養蚕業が台頭し、明治三十年代から前二者に代わる地方産業とした発展してくる。
この地方の養蚕業は、明治のはじめごろわずか自家用の程度であったとも伝えられている。
ところが、明治政府の殖産興業政策に基づく軽工業の近代化とともに、生糸・絹織物の輸出の好調を反映して、この地方の村々にも盛んに養蚕が取り入れられてくる。
先進地の大阪から巡回教師を招いて、桑畑の管理や蚕の飼育方法など新技術が導入され、その振興計画が着々とすすめられている。
蚕業講習会などくり返し実施されるなかで、夏・秋蚕二回の飼育が一般化することによって、ようやく養蚕農家に相当の現金収入をもたらすようになってくる。
しかし、ほどなく第一次世界大戦後の生糸の暴落、繭価不安定期の掛け目取引、アメリカでの人絹糸発明による輸出市況の悪化など、不利な事情が相次いでおき、農家の副収入源であった養蚕も徐々に衰退していく。
とくに、太平洋戦争に突入したころには、食糧の増産のため桑畑が甘薯畑となり養蚕が消滅してしまう。