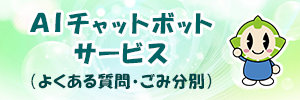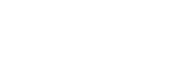本文
(2)農家の副業から発展した工業
近代産業の発展と人びとのくらし
(1)農産物の変遷と農家の経済
(2)農家の副業から発展した工業
香芝市内における金剛砂の採掘と加工、鋳物の製造という二つの伝統産業については、すでに中世の項でとりあげたが、ここでは他の近代になってからの工業の発展についてふれてみたい。
江戸時代以来のこの地方の綿花の栽培に関連して、綿織物の製造が農家の副業として栄え、多くの農家の主婦は木綿織屋の賃織りに従事した。
その伝統は綿花栽培が急速に減少した明治二十年代になっても、輸入原綿の紡績糸を使用して続いていた。
明治三十七(一九〇四)年当時の下田村では製造家九軒、賃織二百六十四名、手機織り三百八名で、年間十万九千九百五反の木綿が生産されている。
それが大正元(一九一二)年の資料では、家内工業十軒、織家七軒、賃織農家二百五十四戸となり、家内工業として木綿生産の専業化が目立ってくる。
しかし、その後間もなく第一次世界大戦となり、戦後の恐慌で大都市の近代工場の生産に圧倒され、伝統の木綿織りは没落する。
この没落した木綿織りに代わって、大正時代の中ごろから新しく貝釦やメリヤス製造の家内工業が市内の各地に導入される。
なかでも靴下の製造業は、旧陵西村(現大和高田市)や旧馬見村(現広陵町)の先進地から、当町の先駆者によって取り入れられ操業されはじめる。
その靴下産業は、幾多の苦難の時代を経て、副業的な形態から脱皮しながら着実に発展し、昭和五十年ごろに郷土の重要産業の地位を確立していた。
しかし、従業員数によってその規模を詳しくみると、一人~三人規模の工場が過半数を占め、まだ家族労働を中心とする個人経営の実態があった。
昭和四十九(一九七四)年の香芝町の工業統計では、製品の出荷額のトップに立っていたのが靴下製造を中心とする繊維工業で、約五分の一の大差で金属製品製造業が続き、電気機械製造業、窯業土石製品製造、パルプ・紙・紙加工品製造業など上位を占めている。
これら工場の分布をみると、その多くは国道百六十五号線とJR・近鉄沿線にあたる、交通機関の発達の早かった地域に集中する傾向があった。
ところが、最近、西名阪道が敷設されそのインターに近い地域や新設道路網の通じた地域に、新しい工場の進出が目立ってきている。