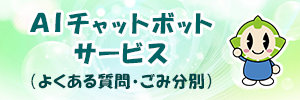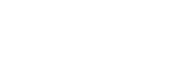本文
(3)商業の変遷と発展
近代産業の発展と人びとのくらし
(1)農産物の変遷と農家の経済
(2)農家の副業から発展した工業
(3)商業の変遷と発展
江戸時代の農村では自給自足の生活を基本としながら、上層の地主階級を中心に、油屋、酒屋、木綿織屋、藍染紺屋など、各種の商品生産がすすめられてきた。
しかし、江戸や大阪のように見世棚を構えた専業の商家はきわめて少なく、前記の製造業者のほか古手屋・小間物屋など、大抵は販売の特権をもつ一部の株仲間に限られていた。
ところが、江戸時代の終わりごろから明治になると、貨幣による交換経済が一般化し、農村でも商品の流通が盛んになってきた。
その影響を受けて、この地方の中心であった下田では、毎月の四日と正月前の十二月二十五日、盆前の七月十日に市が開かれ、大正の中期ごろまで続いたといわれている。
一方、大阪鉄道(現JR)の開通した明治二十四年ごろから、下田付近では商家ができ、市場とともにこの地方の商品流通の中心となった。
現在、大字下田に「市場」の地名があり、そこの地蔵堂から南へ百メートルほどの間で、盆と正月前のごとお(五・十)日に、約七十の出店が日常品や衣料品の市を開いたと伝えている。
しかし、この下田の市も昭和二年の近鉄大阪線の開通によって、その姿を消し、ごとお(五・十)市や定期市に代わって各種の商店が増加してきた。
その後、鉄道の下田駅付近や近鉄線の駅前を中心に商家が増加し、人びとの生活に密着して各種の商業が発達する。
その商業の発達に関連して、明治二十九(一八九六)年、高田銀行が開設され、大正八(一九一九)年には五位堂村信用購買販売組が他地域に先んじて営業を始める。
これら金融機関は、以後合併と変遷の経過をへて、現在の南都銀行や農業協同組合となっている。
昭和四十九年の商業調査によれば、町内の総商店数二百九十五、そのうち小売商は二百四十一を占め、卸売業が十二、飲食店四十二となっており、規模別には従業員四人以下の零細企業が全体の約九十五パーセントを占めている。
このことは、鉄道交通の発達にともなう、大都市を中心とする商圏の拡大に主な要因があり、日常生活の最寄品以外は町外で充足する比率が高くなった結果とも考えられる。
しかし、市内の各地に新しい団地が作られ、とみに人口の増加傾向が目立ってきた。
その人びとの需要に応えるために、新しい商店やスーパーの誕生がみられ、商業や金融業の発達にめざましいものがある。
かつて、下田で市が開かれ地域住民の生活と結びついて、「下田よいとこ大和の江戸や、お宮三社に寺五つ」といわれたような活況ある流通の中心を、新しい都市づくりの中に位置づけて、一段と地域の商業が発展することを祈りたい。