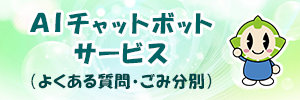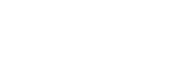本文
(4)近代化への歩み
近代化への歩み
(1)明治の政変と奈良県の成立
(2)大・小区制度と旧村の伝統
(3)地方制度の再編成
(4)近代化への歩み
明治の新政府は、幕藩時代の旧弊を一新することを標ぼうしていたが、維新当初の人びとのくらしのなかには、依然として封建的な色彩が強く残されていた。
同時に新政府の諸施策は、民衆の期待に反したものが少なくなかった。
慶応四(一八六八)年三月十四日、新政府は江戸城の総攻撃を予定していた。
その前日、かの有名な「五ヵ条の御誓文」を公にする。
その内容は極めて進歩的と思われる政治の根本方針に関するものであり、新政への国民の支持を集める意図がうかがえる。
しかし、同じ日に、旧幕府の高札であった「五傍の掲示」にとりかえ、それには、徒党を組んで強訴や逃散することを禁じ、キリシタン宗門の信仰を許さず、住民の浮浪と本国脱走(移住)を禁止するなど、国民の行動を極めて高圧的に制限している。
こんな新政府の矛盾した施策は、香芝市内に残されている文書でもうかがえる。
明治三(一八七〇)年三月、江戸時代と同じように、まだ宗門改めの寺請制度が逢坂村で実施されており、年貢の収納についても本途物成・小物成など旧法と変わらない方式がとられている。
また、庄屋・年寄・百姓代など村役人や五人組の制度なども従来通り受け継がれていた。
こうした維新当初の状態から、近代化をめざす政府は、きわめて不充分ではあったが社会の古い制度を徐々に改めていく。
そのいくつかをあげると、四民平等と戸籍法の制定、地租改正と徴兵制の実施、文明開化と学制の発布などがある。
なかでも四民平等については、封建的な身分制度の撤廃を打ち出して、かつて支配階級がもっていた武士の特権を廃し、一般に姓を名のることを認め、乗馬や羽織・袴の着用、住居の移転や職業選択の自由を認めるようになった。
このとき、特権のなくなった士族には「秩録公債」を発行して生活を保護したが、幕府が最下層の身分において差別しつづけてきた賎民階級は、大政官による解放の布告が出されただけであった。
そして、二百六十余年の分裂支配のもととなった身分制によって、農民にしみ込んだ被差別部落への差別意識は、解放令に反対する農民一揆さえも生みだし、今日なお日本の真の民主化をはばみつづけている。
国民皆学をめざして明治五(一八七二)年には学制が公布され、翌々年に五位堂宝樹寺に栄商舎、下田真宗寺に誠弘館、逢坂西念寺に健学舎、中筋万善寺に奨道館など、各地の寺院を仮校舎に最初の小学校が創設される。